〒170-0003 東京都豊島区駒込3-20-13-202
JR山手線、東京メトロ南北線 駒込駅 西側(巣鴨寄り)出口から徒歩2分
受付時間
定休日:土曜・日曜・祝日
クリニック開業後のレセプト業務をどう考えるか
~QCDで比較する~

クリニックを開業すると、経営者はすべての業務を管理監督しなくてはなりません。
自身で実施する診療行為のほか、事務処理についても一部は自身で実施し、残りの業務も実施方法を考えなければなりません。
クリニックの事務業務の中で重要性が高く、かつ実施方法も多様な業務として「レセプト業務」があります。
ここでは、QCDの観点から、レセプト業務をどのように実施していけばよいのかについて解説します。
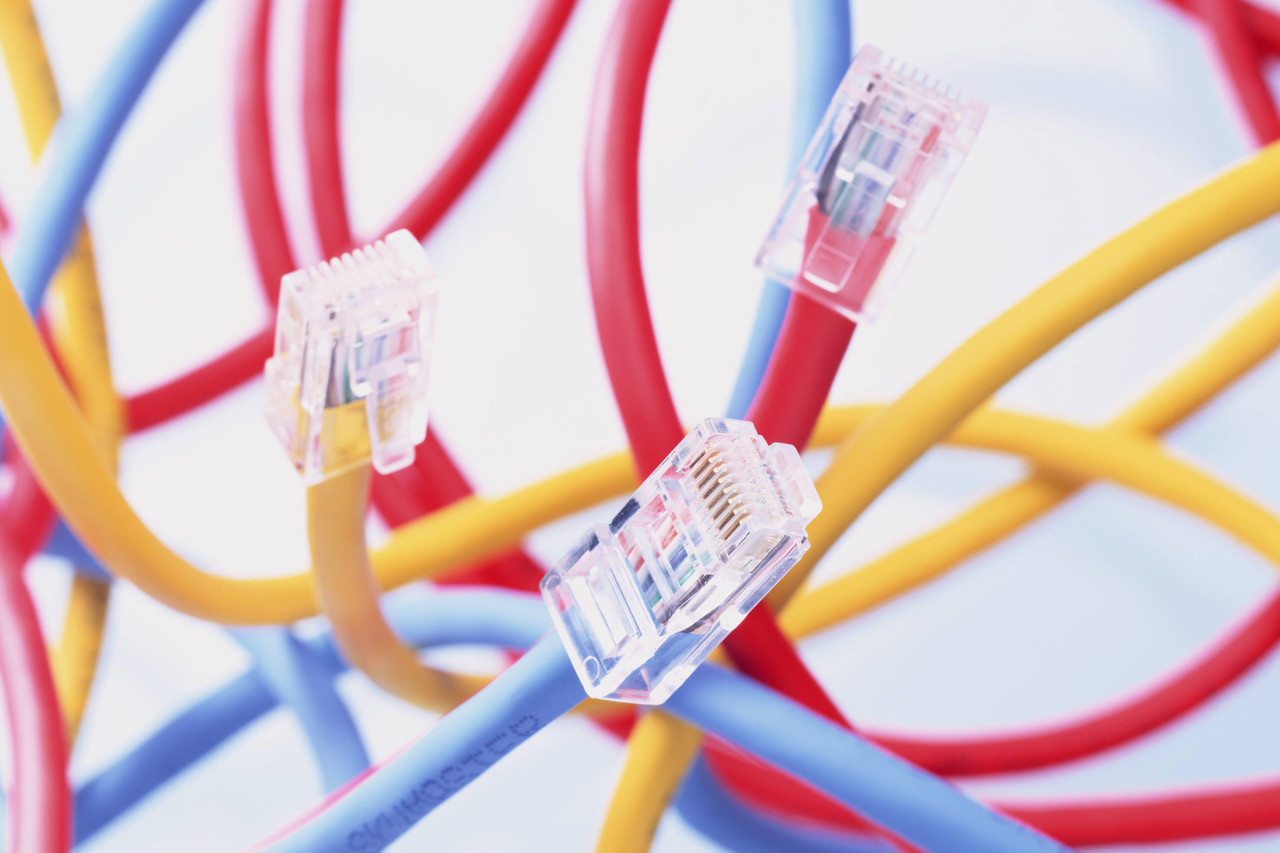
今回、評価指標(というか解説の切り口)として使用する「QCD(キューシーディー)」について最初に解説しておきます。ご存じな方は読み飛ばしてください。
QCDは、元々は製造業の生産管理を行う上で重要な3つの要素の頭文字を取ったものです。
すなわち、
Q=Quality(品質)
C=Cost(コスト)
D=Delivery(納期)
となり、これらを改善すると顧客満足度を向上させることができると言われております。
医療はサービス業なので指標としては適切ではないかも知れませんが、一方では分かりやすい指標なので今回解説の柱として活用させていただきます。
具体的には、
Q=レセプト業務の質(算定漏れ、査定返戻などのミスが少ない)
C=レセプト業務にかかるコスト(誰がどのくらい時間をかけて業務を行うか)
D=レセプト業務の期日管理(〆は決まっているが、どの程度余裕をもって請求するか)
といった観点で解説を行います。

次に、レセプト業務の流れについても簡単に解説します。ここもご存じの方は読み飛ばしてください。
ちなみに、レセプトという言葉は医療業界特有なのでとっつきにくいのですが、要は「月次請求書」です。
医療機関は、レセプト業務を通じて健康保険組合や市町村に対する月次請求書を発行しております。
それだけだと何ら専門知識は必要なさそうにも思われますが、請求を受けた側では請求が妥当かを診療行為ベースで審査します。
その際のルールが専門的なので、レセプト業務にもまた専門知識が求められるという訳です。
前段が長くなりましたが、一般的なレセプト業務の流れは以下の通りです。
0.日々の会計処理
レセプトは月次請求書なので、ベースとなるのは日々の請求結果です。
医療機関では、日々来院する患者の会計処理を行う際に、健康保険組合等への請求データも一緒に作成しています。
(というより、請求データの3割が自己負担、という計算過程となります)
一般的には日々の会計処理はレセプト業務には含めませんが、広い意味ではレセプト業務の一部分とも言えるので流れに含めておきます。
1.月締め後のチェック
月が替わると前月分の患者ごとの診療行為が確定します。
その後、医療機関側では概ね以下のチェックを行います。
(1)病名
診療行為に対して適当な病名がないと査定の対象となります。
よって、検査や薬剤などの診療行為ごとに、病名とのマッチングを行います。
(2)算定漏れ・重複算定
例えば月1回算定できる管理料の算定漏れがないか、逆に2回以上算定していないかなどを確認します。
レセコンのアラート機能などで日々のエラーはある程度予防できますが、月でまとめた時に生じるエラーを修正します。
(3)査定・返戻行為
直近の査定・返戻情報を確認します。
これらは単純ミスもありますが、「請求可能だと思っていたが不可だった情報」でもあります。
よって、これらから得られる情報を次回レセプトに反映させ、同じ過ちを繰り返さないようにします。
2.保留・月遅れ請求処理
患者の保険証情報を得られていないなどの理由で請求を遅らせたり、前月以前に遅らせた分を請求したりします。
保険証情報がない状態で請求しても100%返戻となります(請求書でいえば請求先がないので当然ですね)。
以前に請求しなかった分については、情報が得られ次第請求しないと報酬を得ることができません。
よって、これらの処理もレセプト業務を構成する重要な作業となります。
3.査定・返戻への対応
戻ってきた査定・返戻情報は翌月以降のレセプトに反映させるべき情報ですが、それ自体への対応も必要です。
すなわち、追記・修正を行って再請求をしたり、査定の原因を調査して不備がないと判断されれば再審査請求を行ったりします。
これらの情報は今でも紙ベースでやり取りされるので、1.2.と並行して別の流れで作業を行います。
4.請求処理
一般的には電子的に請求を行います。
レセコンから所定の様式をエクスポートし、それを電子申請システムにアップロードするという、基本的には単純作業です。
(たまに意味不明なエラーがでると予定外の時間がかかるくらいです。)
申請後の証票を印刷・保管してレセプト業務は終了となります。
まずはQCDの中で最も大切な品質の視点です。
レセプト業務の流れは前述しましたが、レセプト業務を「誰がやるのか」については以下のような選択肢があると思います。
1.全て経営者(医師)が実施する
診療行為に対する知識が最も豊富です。
開業前の勤務先で何らかの形でレセプトに関与していることも多いと思われます。
よって、一般的にある程度の質は担保できそうです。
ネックは他業務との兼ね合いで、普通は診療に専念した方が経営的なメリットが大きいです。
現実的には、こういう業務が好きな一部の医師を除くと、このようなやり方をしているクリニックは少ないと思われます。
2.一部を経営者(医師)が実施する
病名チェックや提出前の最終チェックなど、重要と思える部分を医師が行うパターンです。
1.よりネックは少なくなり、複数の目が入るので1.より質も担保できるかもしれません。
何より、「レセプト業務がブラックボックス化しない」という点で有効な業務のやり方です。
3.全て医事担当者が実施する
月次請求業務=事務作業なので事務に丸投げしたいというニーズから、医事担当者にすべてを任せているクリニックも少なくないです。
経験者を採用して任せておけば楽で質も担保できるという考え方です。
ただ、これは質的なリスクもまた大きいと考えます。
医事担当者の質を担保するのは「採用面接時のやり取りと履歴書」ということになります。
クリニック開業時の採用面接でも記載しましたが、レセプト業務はそれなりの規模の病院でも最終作業はほぼ1人で行っています。
よって、レセプト業務経験者でも最初から最後までの作業を経験していない場合もあります。
また、施設によってレセプト業務の実施方法(レベル)もまちまちで、医療機関の大きさや医療提供レベルなどからは判断不能です。
何より、特定の医事担当者にレセプト業務を任せてしまうとレセプト業務がブラックボックス化します。
実はミスが多いのに隠ぺいする、必要のない残業をする、退職を盾に条件交渉をされるなどのリスクが生じます(これで相談を受けるケースも少なくないです)。
4.一部または全部を外注する
派遣・委託・コンサルなど業者の活用度合いも色々あります。
専門家が関与するので質的には良さそうですが、全部任せてしまうと3.と同様に業務内容がブラックボックス化します。
また、これら業者も玉石混交なので、質を担保するのは実は結構難しいです。
更に、同じ業者でもエキスパート級の職員ばかりを揃えている訳ではないので、担当者によっても質がばらつきます。
一方で常勤職員を採用するより手軽な面もあるので、一時的に欠員が生じた際や、経験者が雇用できない際の教育などで一定期間利用するのは有効だと思われます。
上記より、質を担保するためには経営者又は外部業者がレセプト業務の一部を担い、医事担当者の業務がブラックボックス化しないようにすることが肝要です。
Q(品質)と同じ選択肢でC(コスト)についても検討します。
医事担当者はレセプト業務実施の有無にかかわらず日々の窓口対応でも必要という前提で、レセプト業務のコストは「医事担当者の残業時間」「外部業者に支払う費用」とします。
1.全て経営者(医師)が実施する
上記で定義したコストは発生しません。
但し、医師がレセプト業務を担うことで診療に投じる工数が減る場合、それらはコストとなります。
(例えば「毎月〇日はレセプト業務のため午後休診」とすれば、減収分は実質的にはレセプト業務のコストとなる)
通常は診療時間外のサービス残業(経営者なので残業は発生しない)で対応するのでコストが生じない場合が多いと思いますが、ワークライフバランスの観点からはお勧めできません。
あくまでこういった事務処理を自分でやりたい方のみが適用すべき方法だと考えます。
2.一部を経営者(医師)が実施する
医師の負担も1.程ではないものの発生し、医事担当者の残業代も生じます。
ただ、業務の流れを把握できるので無駄な残業などはコントロールしやすい方法です。
1.と比較し、医師の負担を医事担当者の残業代で買うような考え方となります。
(1.と比較し医師の業務が5時間減り、医事担当者の残業代が10,000円増えた、等)
上記のように、費用対効果を考えつつレセプト業務を管理できれば非常にコスト面でも有用です。
3.全て医事担当者が実施する
多くの場合で残業代が発生し、しかもそれが妥当なのかを判断できないのが難しいところです。
もっとも、月数時間程度の残業であればさほどのコストにはならないので、必要なコストと割り切ってしまうという考え方もあります。
枚数や人員体制などにもよりますが、レセプト業務だけで10時間を超えるような残業を請求される状態が続くようであれば、業務の全容を把握できるような何らかのアクションを検討しましょう。
4.一部または全部を外注する
一般的には最もコストがかかります。
これらの活用は臨時的なものとしましょう。
医師の最終チェックなどを外注する場合、自身の手間の減少度合いとかかるコストから費用対効果を検討しましょう。
上記より、効率よく業務を行ってくれる医事担当者を採用できるのであれば全て医事担当者にお任せでも良いのかも知れませんが、そうでない場合には業務を管理できるようなアクションを検討しましょう。
サービス業だとイメージしにくいですが、D(納期)についても見てみます。
レセプト業務については、最終納期は毎月10日頃(暦によって多少変わる)と決まっています。
が、クリニック内での請求日をいつにするかはまちまちです。
ここでは、納期と関連してレセプト業務のスケジューリングについて解説します。
1.スケジュールを作成しよう
管理上も有効なのは「スケジュールを作成する」事です。
最低でも「〆⇒請求日」をカレンダーに記入するなどの見える化を図りましょう。
電子申告の場合、月初5~10日の間に処理を行う必要がありますが、私の場合は概ね月初から5労働日で請求という「早めに仕上げる」やり方で実施していました。
早めに仕上げるメリットは、
(1)通常業務に早くに戻れる
(2)スケジュールが多少タイトの方が作業効率を考えるようになる
(3)不測の事態があった場合にもリスケしやすい
といった事が挙げられます。
〆日の考え方はクリニックによってもまちまちですが、いずれにしてもスケジュールを見える化して効率よくメリハリの利いた仕事をできるようにしましょう。
2.日々の業務を大切にしよう
前述しましたが、日々の業務からレセプト業務は始まっています。
極端な話、日々の業務を完璧に実施できるでのあれば、レセプト時期のチェック作業は不要ということになります。
電子カルテやレセコンに備えられたチェック機能なども徐々に精度が上がってきています。
レセプト時期のチェック事項を日々の診療後や診療の合間に潰す事で、レセプト時期の作業負荷は大きく軽減でき、かつ質も向上します。
日々が締め日のような感覚で業務を実施してもらえるようにしましょう。
3.チェックのやり方を管理しよう
10日まで時間があるので、質を上げるのであれば期限ぎりぎりまでチェックを繰り返すという医事担当者も見受けられます。
一方、チェック業務の費用対効果は一般的には時間とともに低下します。
(1回目より2回目の方が、かかる時間のわりに修正項目が発見されにくい)
チェック業務には、その医事担当者の責任感・性格が如実に現れます(まれに、悪質な残業代稼ぎの場合もあります)。
過剰なチェックについては、経営者側でやらないように言わないとコスト増加の一因となります。
また、必要以上にレセプト業務に時間をかけると、レセプトを担当していない職員の業務負荷が増え、職場内不満の要因にもなります。
チェックが合理的なやり方・回数・時間になっているのかは担当者へのヒアリングで分かるので、無駄な業務を発生させていないかを管理するようにしましょう。
それでも経営管理や会計税務にお困りなら

代表税理士 加藤 二郎(かとう じろう)です。お問い合わせをお待ちしております。
最後までお読みいただきありがとうございます。
税理士事務所Craveは、医療・クリニック専門の税理士事務所です。
・開業にあたってどのような準備をしたらよいか分からない
・現状の顧問税理士が期待に沿った仕事をしてくれない
・経営上の悩みごとがある
等でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問合せください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
新着情報・お知らせ
https://nitoryu26.com/
今までありがとうございました!
https://www.zeip.jp
税理士事務所Crave

住所
〒170-0003
東京都豊島区駒込3-20-13-202
アクセス
JR山手線、東京メトロ南北線 駒込駅 西側(巣鴨寄り)出口から徒歩2分
駐車場:無し
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日


